|
3. ネリーの手入れによって、庭園は見違えるように青々となった。 「今は若い苗ばかりだけど。春になったら一斉に花が開くの。きっとよ」そう言ってネリーは熱心に苗を運んでは世話をした。 庭が日々変わっていくのと同時に、屋敷の内にもどこかしら違った風が吹き込んでくるようだった。 にぎやかで遠慮を知らない少女はよく喋り、よく笑う。老技師やその弟子たちとの間にも壁はなく、すっかり打ち解けたようだった。庭仕事の後は必ず屋敷の当主である彼の元へ一日の報告に訪れ、ティータイムを過ごしている彼とアリスに好きなだけ喋って帰って行く。 ころころと表情の変わる少女は見ていて飽きることがなく、屈託のない性格は周りまで明るくするようだった。 ネリーの言葉遣いも奔放な態度も一向に改善されることはなかったが、彼はいつしか、時間になると少女の来訪を心待ちにするようになっていた。 変わらないのは、もの言わぬ機械人形<ドール>たちだけだった。 月が満ちて、村に祭りの日が訪れる。 ネリーがこれまで丹念に世話をしていた一夜の花は、日暮れとともに見事な大輪の花を咲かせた。 「祭りの当日に花が咲くよう調節するのが、庭師の腕の見せ所なのよ」 老技師に渡された角灯を屋敷の門前に吊るし、大輪の花を前にして、ネリーは得意げに言った。 「ネリー、今日までご苦労だった。お前も村に戻って祭りに行って来るといい」 いつまでたっても花の前から動こうとしないネリーに向かって、彼はそう声をかけた。 「あたしはいいの。今日はここにいたいから。それにこの花、アリスさんに見せてあげたいし」 アリスはドールの一斉調整のために、午後から彼と行動を別にしており、この場にはいないのだった。彼はネリーの好きにさせようと思ったが、いつもと同じように明るく振る舞うネリーの横顔にどこかかげりがあるのを目にとめた。 ネリーがふと顔をあげる。 「ねえ、旦那さんは? 旦那さんはこの花を見てどう思ったの?」 「別にどうとも思わない。何も変わりはしない」 「嘘。旦那さん、この花のこと、一度もはっきりと見てくれてないじゃない。ちゃんと見ないで綺麗かどうかなんてわからないよ」 ネリーの声はいつになく真剣なものだった。彼は少女の前の白い花に目を移した。だがどういう訳か、どうしても目を逸らさずにじっと見続けることができなかった。 「花は駄目だ。花など一晩で枯れていく。すぐに枯れてしまう」 「だから綺麗なのよ」 ネリーはそっと白い花に手を添えた。 「短い間でも一生懸命咲いたの。今しかないの。変わっていくから綺麗なの。ちゃんと見てあげなきゃ可哀相よ」 アリス ―― 。 なぜか彼の目の前にはアリスの姿がはっきりと浮かんだ。 そうして彼は、白い花を美しいと思った。 宵闇が深まるにつれて、村中に角灯の光が点々と広がっていく。家ごとに丹精込めて育てられた一夜の花がいっせいに花開いた。月の光と角灯の灯りに照らされた花々は、どこの家の前でもぼんやりと白い光を放っていた。 「あたし・・・・・・明日からもうこのお屋敷に来れないの」 少女はぽつりと言った。 「兄さんの仕事先のお得意さんで、あたしをもらいたいって言ってくれてる人がいるの。だからもう、ここには来れないんだ」 彼は怪訝な顔をした。 「なぜだ。結婚をしてもこの屋敷には来ることができるだろう」 「来れないよ。あたし一家の奥さんになるんだよ。家の仕事だけをするの。ここに来るのは楽しかった。好きな土をいじっていられたし。 ここの人はみんな親切にしてくれたから。アリスさんのことも旦那さんのことも好きだったよ。旦那さんはみんなみたいに目に見えて優しくしてくれた訳じゃなかったけど、それでも時々さりげなく気遣ってくれたよね。あたしそれが嬉しかった。本当に感謝してる」 「お前は、それで幸せなのか」 「幸せに決まってるじゃない。あたしをもらいたいって言ってくれてる人がいるんだよ。こんな幸せなことなんてないよ」 「ネリー。お前は、その人のことが本当に好きなのか」 ネリーは何とも言えない表情で、彼の方を見た。 「旦那さんは、いじわるだね。 だって仕方ないじゃない。あたしの家にはまだ小さな弟や妹たちがいて、生活だって楽じゃないし。それに、兄さんだって好きな人がいるのにあたしが嫁ぐまで結婚しないつもりなの。 兄さんは、口に出して言ったりしないけどあたし知ってるの。あたしいつまでもあの家にはいられないよ。他に、行くとこなんてないんだもの」 「ではここにいるといい」 彼の何でもない言葉に、ネリーはこれ以上ないというほど目を見開いた。 「そんなの無理だよ。あたしもう来れないって言ったじゃない。何度も言わせないでよ。言いたくないの」 「ここでやりたい仕事をすればいい。意にそまぬ結婚をすることはない。お前が本当に好きな人が出来たら、その時は出て行けばいい。それまでここにいなさい」 ネリーは泣きそうな顔をした。 「あたし本当は旦那さんが好きだよ。誰よりも好きだよ」 「ではここにいるといい」 彼は、先程と何ら変わらない口調で言った。ネリーは泣いているような笑っているような複雑な顔をして、それからやっぱり笑った。 「今日はもう帰りなさい。アリスは来ないかもしれないから」 まだ花の側を離れようとしないネリーを家に帰してから、彼はしばらく一夜の花を眺めていた。 肌寒さを感じ、室内へ戻ろうと振り返ると、いつからそこにいたのか、アリスが夜の闇のように静かに佇んでいた。 「アリス。調整は終わったのかい。ご覧、綺麗な花だよ」 美しい機械人形<ドール>は硬質な瞳でじっと花を見ていた。 「アリス・・・・・・。明日からネリーをこの家に入れることにしたよ」 「それならば、わたくしは、ネリーさんのことを奥さまとお呼びすればよろしいのでしょうか」 「そのような改まった呼び方など必要ない。ネリーはネリーだ。今までと変わらず呼べばいい。今までと何一つ変わらないんだ。アリス」 「わたくしは」 そこまで言葉を発して、アリスは突然ネジが切れたように口を動かすのをとめた。 「アリス、一つだけ訊きたいことがある。お前に、機械人形<ドール>たちに心はあるのだろうか」 「心などございません、旦那さま」 彼女はそう言って精巧な顔に、上手に笑みを浮かべた。 次の日の朝、アリスは挨拶に現れなかった。それどころかアリスの姿は屋敷のどこにも見当たらなかった。 不思議なことに、屋敷の門前で枯れているはずの一夜の花も、鉢ごと一緒に消えていた。 昨日の点検の際、アリスに欠陥はなく、機械人形<ドール>が主人<マスター>の傍を離れて敷地の外へ出るなど考えられないことだと技師たちは慌てた。 後に、アリスと彼の最後のやりとりを聞いた老技師は、ドールがそのような質問に答えることなどありえないと証言したが、アリスはついに見つからなかった。 新しくアリスをもう一体造ることは可能だと技師は幾度か提案したが、彼が応じることはもう二度となかった。 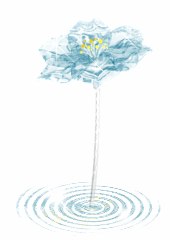 fin. fin.
|